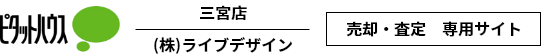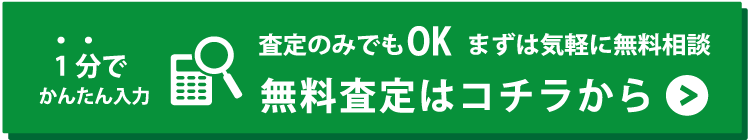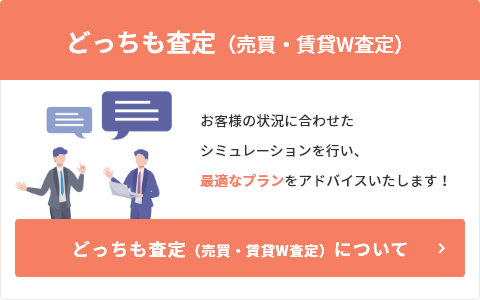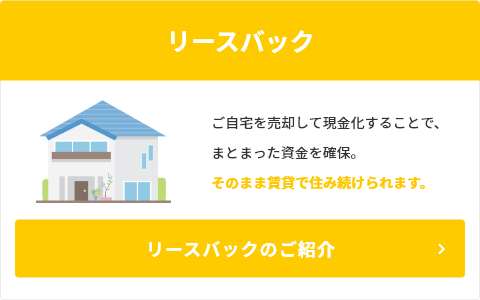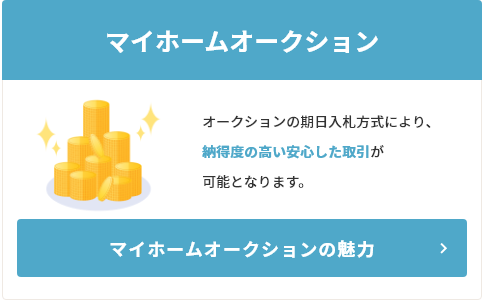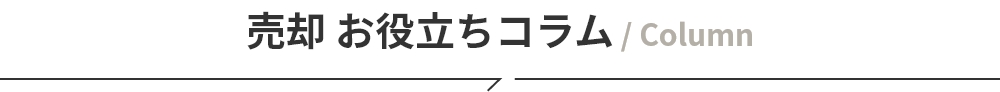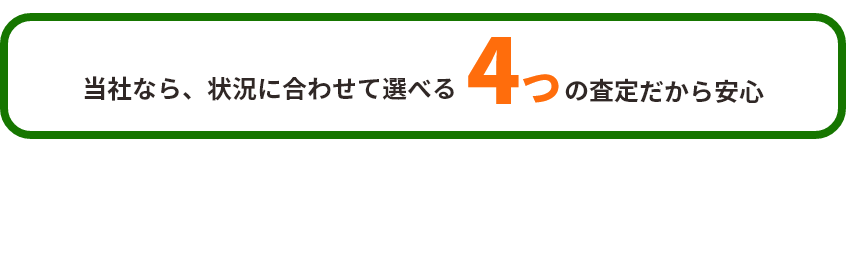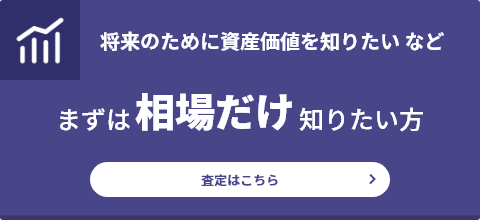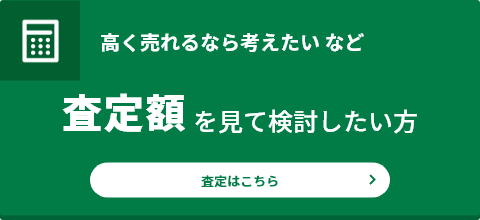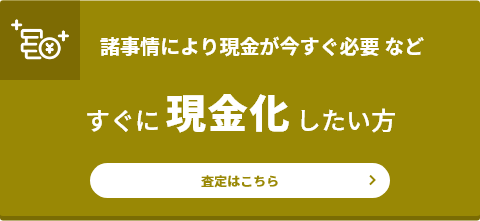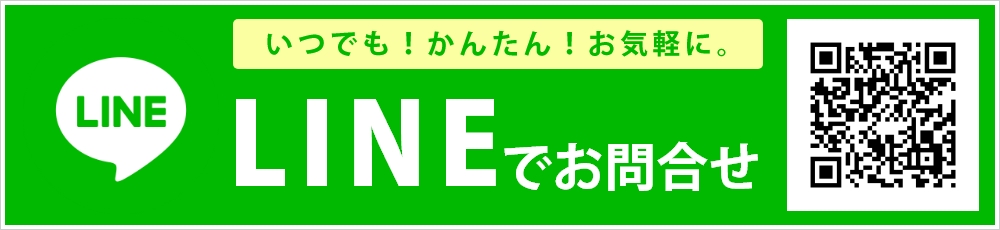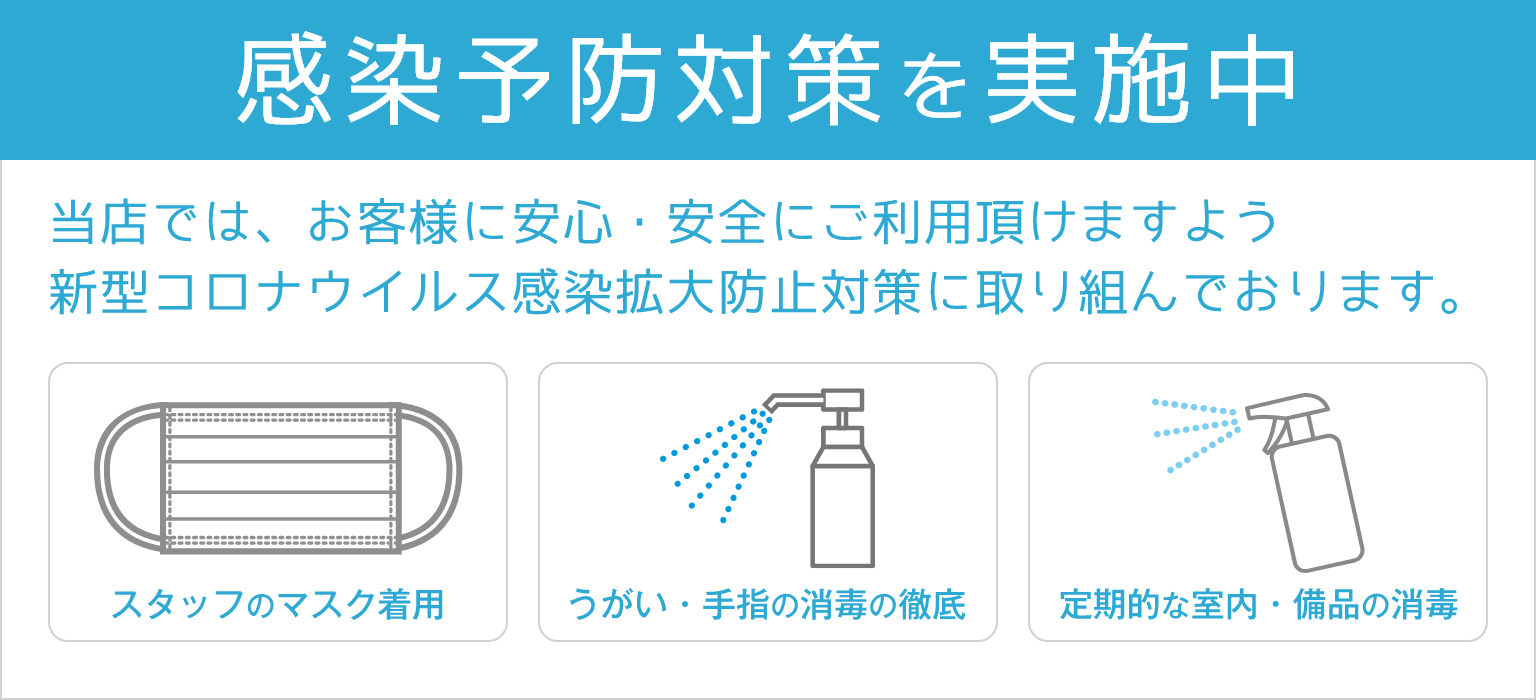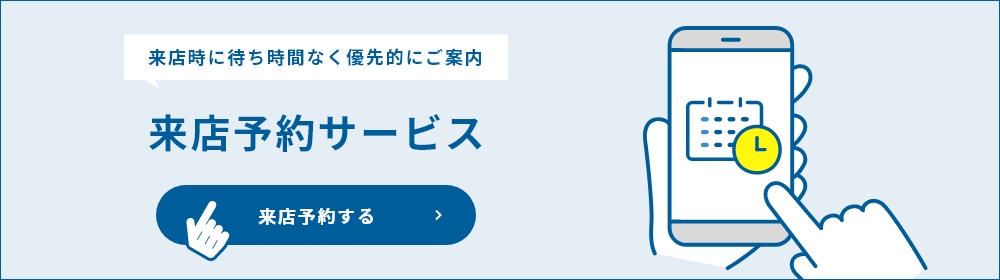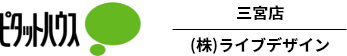更新情報
- 2024/10/22
- 【査定依頼】神戸市須磨区大田町3丁目 グレイスハイツ板宿の査定依頼をいただきました
- 2024/10/21
- 【査定依頼】神戸市灘区五毛通1丁目 戸建の査定依頼をいただきました
- 2024/10/19
- 【査定依頼】神戸市須磨区行幸町 オーシャンテラスの査定依頼をいただきました
- 2024/10/17
- 【査定依頼】神戸市兵庫区下祇園町 下祇園コーポの査定依頼をいただきました
- 2024/10/15
- 【査定依頼】神戸市須磨区北落合 ライオンズマンション須磨名谷の査定依頼をいただきました
- 2024/10/13
- 【査定依頼】神戸市中央区山本通 ジオ神戸山本通の査定依頼をいただきました
- 2024/10/11
- 【査定依頼】神戸市灘区楠丘町1丁目4-20 エクセルシア楠丘の査定依頼をいただきました
- 2024/10/09
- 【査定依頼】兵庫県神戸市東灘区住吉本町 戸建の査定依頼をいただきました
- 2024/10/07
- 【査定依頼】兵庫県尼崎市西立花町 戸建の査定依頼をいただきました
- 2024/10/05
- 他社で買取不可と言われたボロ屋敷も買い取ります!
当店の特徴
神戸市の不動産売却・買取はお任せください
神戸市と周辺エリアの不動産売却・買取・査定はお任せ下さい。
神戸市のピタットハウス加盟店・ライブデザイン・グループは、神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区を中心とした神戸市と兵庫県の周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
神戸の一戸建て・土地・マンションの売却・買取はもちろん、収益物件・事業用物件・リゾート物件の売却・買取も、対応可能です。
また、神戸市から離れた兵庫県内・県外でも、日本全国のピタットハウスのネットワークを通じて販売活動が可能です。
不動産売却や買い取りをご検討される理由は、お客様によって様々です。どんな事でも遠慮なくご相談下さい。
不動産査定は、無料で秘密厳守で実施致します。
神戸市周辺エリアの不動産のご相談は、神戸市の地域密着型不動産会社・ピタットハウス加盟店のライブデザイン・グループにお任せ下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
ライブデザイン・グループについて
平成19年に神戸にて産声をあげた当社は、創業時より他の不動産会社とは違うサービスを目指し賃貸仲介業を中心に事業を展開してまいりました。「お客さまにとって私たちが出来るサービスとは何か?」を追求していった結果、現在は賃貸仲介、売買仲介、不動産買取、販売、リノベーション事業など幅広く展開しています。今後私たちは今のサービスにとどまらず、総合不動産業として、これから起こりうるであろう業界の変化をいち早く感じ取りながら、時代の流れに沿ったかたちでお客さまに最高のサービスをご提供する事をお約束致します。
不動産販売活動について
お客様からお預かりした大切な不動産は、当社自身での販売活動はもちろんの事、近隣の不動産会社ネットワークを通じて、お客様の不動産を一番としてくださる方に届くように販売活動を実施いたします。
今、ご覧いただいているホームページは、「不動産売却 買取をお考えの方」向けのホームページです。
お預かりした不動産は、当社の「購入をお考えの方」向けホームページや、その他の各種媒体で、ご紹介させて頂きます。
(※ 売却をしている事を大々的に知られたくない場合は、ご相談下さい。そのように対応させて頂くことも可能です。)
当社の「不動産販売」活動状況は、こちらから、ご覧いただけます。
また、当社は、賃貸部門が有ります。
この活動の中で、このエリアで、既に、複数の賃貸物件を所有しているオーナー様や、このエリアで、賃貸物件で、資産運用をしたいと考えているお客様との繋がりが有ります。
中古マンションの一室(区分所有)や、中古戸建の貸家も、人気が有りますので、実際に自分が住む為のお客様だけでなく、資産運用として購入を検討されるお客様にも、アプローチ出来ます。
是非、当社にお声掛け下さい。
- ピタットハウス姫路駅南口店
- ピタットハウスJR尼崎駅南口店